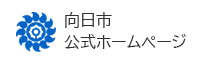ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
向日神社本殿
概要

「向日神社本殿」は、応永25年(1418年)に事始めを行い、同29年(1422年)に上棟(建築)され、創建年時が確実な室町時代の代表的な流造(ながれづくり)の建築物です。 本殿は、三間社流造(さんげんしゃながれづくり)、檜皮葺(ひわだぶき)で、梁間(はりま)5.62メートル、梁間の主屋3.24メートル、前庇(まえびさし)2.77メートルを測ります。正面三間の柱間のうち、中央間のみを戸口とし、両開きの板唐戸を設け両脇間に寺院建築に見られる連子窓が付くことが特徴です。 附(つけたり)として、棟札5枚があり、物集女や寺戸など現在の向日市周辺七郷の人々の名が記され、共同の鎮守であったことや天保年間に大改修が行われたことなどがわかります。 明治35年(1902年)7月31日に、国宝建造物に指定され、昭和25年(1950年)に現在の文化財保護法のもとで重要文化財となりました。
所在地
向日町北山、南山
所有者・管理者
向日神社
地図情報
大きな地図で見る(Googlemapページへ)<外部リンク>