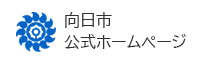ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
紙芝居 京都・向日市の戦国時代
紙芝居 京都・向日市の戦国時代「西岡衆の活躍」
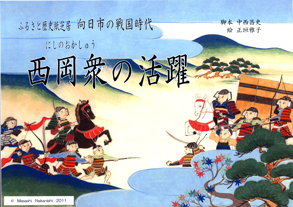
室町時代、向日市周辺は「西岡(にしのおか)」という名で知られていました。西岡の村々には、地域の指導者である武士「国衆」がおり、西岡の国衆は「西岡衆(にしのおかしゅう)」とも呼ばれました。
西岡衆は集団で力を合わせて地域を治めており、農業などにも従事しながら、いざというときには将軍のもとに駆け付けて戦うなど活躍をしていました。
しかし、織田信長の圧倒的な武力により、西岡衆をはじめとする人々の暮らしは大きく変化し、やがて西岡衆が治めていた時代は終わりを告げます。
戦乱の世を力強く生きた西岡衆の活躍を子どもたちに伝えたいと、京都乙訓ふるさと歴史研究会の中西昌史さんが紙芝居を制作しました。表紙を含めて14ページで構成されており、絵は奈良芸術短期大学日本画研究室で指導をされている正垣雅子さんが担当しました。岩絵の具を使用し、日本画の技法で描かれています。
紙芝居 京都・向日市の戦国時代2「太閤唐入り」
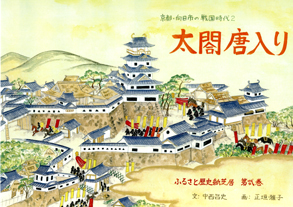
天正20年(1592年)3月、天下統一を果たした豊臣秀吉は朝鮮・明に向け出兵しました。
大軍勢が通った道、西国街道は江戸時代を通じて「唐街道」と呼ばれ、参勤交代の大名行列をはじめ、旅や商いをする人々で賑わいました。
また、豊臣秀吉が休んだ茶屋は、向日町の旅籠「富永屋」として大いに繁盛しました。
江戸時代初期の建物が今も向日神社門前に残されています。
この物語は、京都相国寺の僧が残した日記「鹿苑日録」や江戸時代中期の本「山州名跡志」の記述を参考に、京都乙訓ふるさと歴史研究会の中西昌史さんが創作しました。表紙を含めて13ページで構成されており、絵は奈良芸術短期大学日本画研究室で指導をされている正垣雅子さんが担当しました。