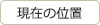
-
- ホーム
- くらしの案内
- 保険・年金・税金
- 国民健康保険(国保)
- 国民健康保険料の決まり方・納め方
国民健康保険料の決まり方・納め方
更新日:2024年6月1日
1年分の保険料
医療分・後期高齢者支援金分
- 所得割(世帯の所得に応じて計算)
- 均等割(世帯の加入者数に応じて計算)
- 平等割(1世帯にいくらと計算)
介護分
- 所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)
- 均等割(第2号被保険者の人数に応じて計算)
- 平等割(第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算)
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方をいいます。
ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる介護分の保険料が不要となります。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合には、14日以内にお届けください。
40歳未満の方
医療分+後期高齢者支援金分
40歳以上65歳未満の方
医療分+後期高齢者支援金分+介護分
(65歳に達する前月までの介護分を年度末までの納期に分けて納めます)
65歳以上75歳未満の方
医療分+後期高齢者支援金分
(介護分は別に納めます)
令和6年度国民健康保険料
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
|---|---|---|---|
| 1.所得割(所得に対して) | 9.31パーセント | 3.17パーセント | 2.97パーセント |
| 2.均等割(1人あたり) | 36,480円 | 12,240円 | 12,240円 |
| 3.平等割(1世帯あたり) | 23,160円 | 7,800円 | 6,000円 |
| 限度額(最高額) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
1年間の保険料=医療分(1+2+3)+後期高齢者支援金分(1+2+3)+介護分(1+2+3)
保険料が限度額を超えるときは、限度額が1年間の保険料になります。
国保料は、世帯主が納付義務者です。世帯主が国保に加入していない場合でも納付義務者になります(この場合、世帯主の所得は保険料の計算には含みません)。
計算例
3人世帯
- 夫(45歳)営業所得(総所得)250万円
- 妻(40歳)所得なし
- 子(15歳)所得なし
の場合
医療分
1.所得割 (2,500,000円(総所得)-430,000円(国保の基礎控除))×0.0931(所得割)=192,717円
2.均等割 36,480円×3人=109,440円
3.平等割 23,160円×1世帯 =23,160円
1+2+3=325,300円(100円未満切捨)…A
後期高齢者支援金分
1.所得割 (2,500,000円(総所得)−430,000円(国保の基礎控除))×0.0317(所得割)=65,619円
2.均等割 12,240円×3人=36,720円
3.平等割 7,800円×1世帯 =7,800円
1+2+3=110,100円(100円未満切捨)…B
介護分
1.所得割 (2,500,000円(総所得)−430,000円(国保の基礎控除))×0.0297(所得割)=61,479円
2.均等割 12,240円×2人=24,480円
3.平等割 6,000円×1世帯 =6,000円
1+2+3=91,900円(100円未満切捨)…C
国保料合計
A(医療分)+B(後期高齢者支援金分)+C(介護分)=527,300円
保険料の軽減
総所得金額が一定以下の世帯には均等割・平等割について軽減制度があります。
所得の申告をされていない場合には、保険料の軽減ができません。
保険料の軽減を受けるためには、被保険者全員と被保険者でない世帯主の所得の申告が必要です。
|
軽減 割合 |
対象世帯の所得要件 |
|---|---|
| 7割 | 前年の世帯の所得合計≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割 | 前年の世帯の所得合計≦43万円+(29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割 | 前年の世帯の所得合計≦43万円+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
被保険者数とは賦課期日(4月1日)における人数で判定し、年度途中における被保険者数の増減は考慮しません。ただし賦課期日後に新規加入された世帯は、加入した時点で判定します。
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国保の被保険者の資格を有する方、及び、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国保の世帯主と当該日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。
保険料の軽減に該当する場合の計算例
3人世帯
- 夫(45歳)営業所得(総所得)100万円
- 妻(40歳)所得なし
- 子(15歳)所得なし
上記の所得で、1,000,000円≦430,000円+295,000円×3人(1,315,000円)のため、5割軽減に該当する場合
医療分
1.所得割 (1,000,000円(総所得)-430,000円(国保の基礎控除))×0.0931(所得割)=53,067円
2.均等割 (36,480円×3人)ー(18,240円×3人)=54,720円
3.平等割 (23,160円×1世帯)ー(11,580円×1世帯) =11,580円
1+2+3=119,300円(100円未満切捨)…A
後期高齢者支援金分
1.所得割 (1,000,000円(総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0317(所得割)=18,069円
2.均等割 (12,240円×3人)ー(6,120円×3人)=18,360円
3.平等割 (7,800円×1世帯)ー(3,900円×1世帯) =3,900円
1+2+3=40,300円(100円未満切捨)…B
介護分
1.所得割 (1,000,000円(総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0297(所得割)=16,929円
2.均等割 (12,240円×2人)ー(6,120円×2人)=12,240円
3.平等割 (6,000円×1世帯)ー(3,000円×1世帯) =3,000円
1+2+3=32,100円(100円未満切捨)…C
国保料合計
A(医療分)+B(後期高齢者支援金分)+C(介護分)=191,700円
未就学児にかかる均等割額の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1を軽減します。保険料軽減措置が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
未就学児にかかる均等割額軽減の計算例
3人世帯
- 夫(40歳)営業所得(総所得)250万円
- 妻(40歳)所得なし
- 子(4歳) 所得なし
の場合
医療分
1.所得割 (2,500,000円(総所得)-430,000円(国保の基礎控除))×0.0931(所得割)=192,717円
2.均等割 (36,480円×3人)ー(18,240円×1人)=91,200円
3.平等割 23,160円×1世帯 =23,160円
1+2+3=307,000円(100円未満切捨)…A
後期高齢者支援金分
1.所得割 (2,500,000円(総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0317(所得割)=65,619円
2.均等割 (12,240円×3人)ー(6,120円×1人)=30,600円
3.平等割 7,800円×1世帯 =7,800円
1+2+3=104,000円(100円未満切捨)…B
介護分
1.所得割 (2,500,000円(総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0297(所得割)=61,479円
2.均等割 12,240円×2人=24,480円
3.平等割 6,000円×1世帯 =6,000円
1+2+3=91,900円(100円未満切捨)…C
国保料合計
A(医療分)+B(後期高齢者支援金分)+C(介護分)=502,900円
産前産後の被保険者への軽減
産前産後の被保険者は、所得割額と均等割額が産前産後期間相当分(4か月分。多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※未就学児にかかる均等割額の軽減も併用して適用されます。
産前産後の被保険者への軽減額の計算例
3人世帯
- 夫(40歳)営業所得(総所得)250万円
- 妻(40歳)営業所得(総所得)100万円
- 子(0歳) 所得なし 出生月 8月
の場合
医療分
1.所得割 ((2,500,000円(夫の総所得)-430,000円(国保の基礎控除))+(1,000,000円(妻の総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0931(所得割)ー(1,000,000円(妻の総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0931(所得割)×4/12(4か月)=228,095円
2.均等割 (36,480円×2人)×3/12(4月から6月の3か月)+((36,480円×2人)ー(36,480円×1人))×1/12(7月の1か月)+((36,480円×3人)ー(36,480円×1人)ー(18,240円×1人)×3/12(8月から10月の3か月)+((36,480円×3人)ー(18,240円×1人))×5/12(11月から3月の5か月)=72,960円
3.平等割 23,160円×1世帯 =23,160円
1+2+3=324,200円(100円未満切捨)…A
後期高齢者支援金分
1.所得割 ((2,500,000円(総所得)−430,000円(国保の基礎控除))+(1,000,000円(妻の総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0317(所得割)ー((1,000,000円(妻の総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0317(所得割)×4/12(4か月)=77,665円
2.均等割 (12,240円×2人)×3/12(4月から6月の3か月)+((12,240円×2人)ー(12,240円×1人))×1/12(7月の1か月)+((12,240円×3人)ー(12,240円×1人)ー(6,120円×1人)×3/12(8月から10月の3か月)+((12,240円×3人)ー(6,120円×1人))×5/12(11月から3月の5か月)=24,480円
3.平等割 7,800円×1世帯 =7,800円
1+2+3=109,900円(100円未満切捨)…B
介護分
1.所得割((2,500,000円(総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))+(1,000,000円(妻の総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0297(所得割)ー((1,000,000円(妻の総所得)ー430,000円(国保の基礎控除))×0.0297(所得割)×4/12(4か月)=72,765円
2.均等割 (12,240円×2人)×8/12(8か月)+(12,240円×1人)×4/12(4か月)=20,400円
3.平等割 6,000円×1世帯 =6,000円
1+2+3=99,100円(100円未満切捨)…C
国保料合計
A(医療分)+B(後期高齢者支援金分)+C(介護分)=533,200円
後期高齢者医療制度創設にともない、国民健康保険料が軽減されます
1.国民健康保険に加入している世帯で、後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
所得の低い方の国民健康保険料の軽減が引き続き受けられます
保険料の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
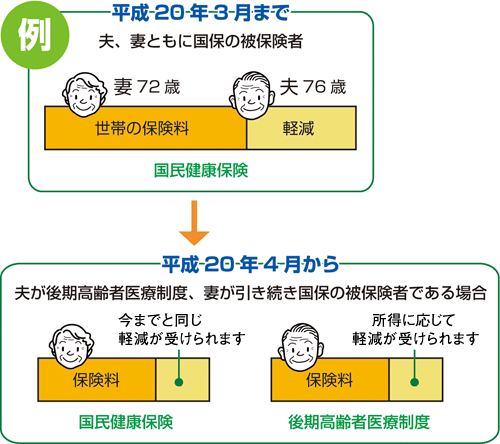
世帯別平等割が半額になります
国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間、世帯別平等割が2分の1に軽減され、その後、3年間、4分の1が軽減されます。
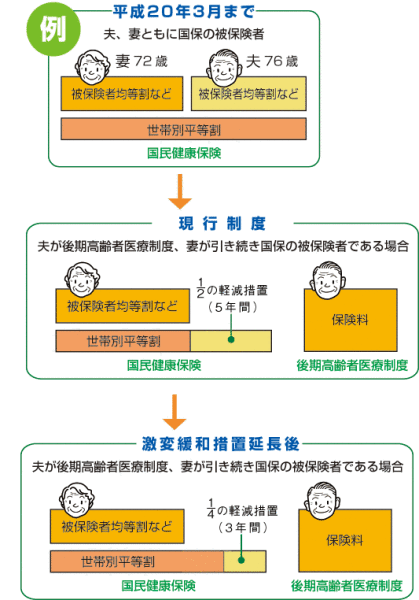
2.会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
申請により保険料の軽減が受けられます
新たに国民健康保険加入し、国民健康保険料を納めていただくことになった方については、市区町村の窓口に申請いただければ、当分の間、所得に応じてご負担いただく保険料が免除されます。また、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、被保険者均等割が半額となり、さらに、被保険者が1人の場合などには、世帯別平等割も半額になります。
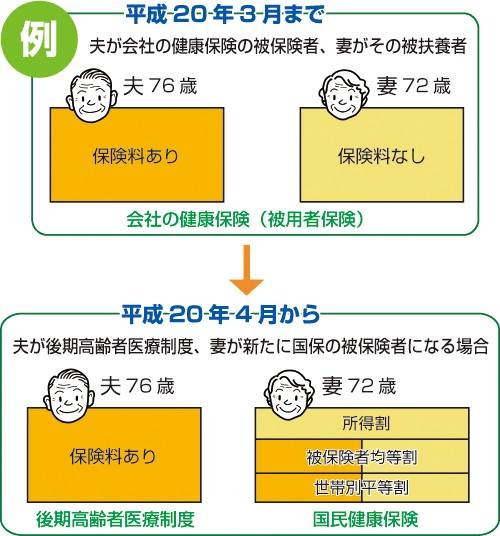
国民健康保険料の納め方
普通徴収による納め方
納付書により銀行などで直接、現金で納付する方法、または、指定口座から自動で引き落としする方法(口座振替)をいいます。
保険料は4月から翌年3月までの12か月分を、6月から翌年3月までの10回(第1期から第10期)に分けて納めていただきます。
保険料は毎月月末(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)が期限となっていますので、期限内に納めてください。
ただし、12月については、納期限が28日(納期限が日曜日の場合は1月5日、土曜日の場合は1月6日)となりますのでご注意ください。
期限を過ぎると督促手数料や延滞金が発生します。
特別徴収による納め方
65歳から74歳の方のみで構成される国民健康保険加入世帯で、世帯主の年金から保険料を天引きする納め方をいいます。
次の要件すべてに該当する場合、特別徴収となります。
- 年額18万円以上の年金を受給している。
- 介護保険料を年金から特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険料を合算した金額が年金額の2分の1を超えない。
特別徴収に該当される方であっても、次の基準を満たす方につきましては、申請していただくことにより、口座振替に変更できます。
- これまで、保険料に滞納、未納がない方
- 現在口座振替による納付をされている方(今後、納付方法を口座振替に変更される方)
関係機関との事務日程があらかじめ決まっており、すぐには変更出来ない場合があります。

-
市民サービス部 医療保険課 賦課収納係(東向日別館3階)
電話 075-874-2793(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ







