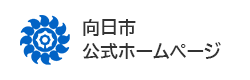本文
令和3年度市長賞入賞作品
なんだろうなんだろう
向陽小学校 二年 清水 璃生 さん
わたしは、『なんだろうなんだろう』を読みました。この本をえらんだりゆうは、わたしが『もうぬげない』という本がすきで、この本を書いたヨシタケシンスケさんの本をさがした時に、絵を見ておもしろそうだったからです。この本は、いろいろなことについて「なんだろう」と考える本です。
わたしがおもしろかったところは、はじめの場めんです。それは「がっこう」ってなんだろうと書いてあるところです。わたしは、「べんきょうするところ」と思いました。本には「たからものがみつかるところ」と書いてありました。わたしとぜんぜんちがうとビックリしました。わたしは、学校でみつかるたからものって、なんだろうと思いました。どんぐり、虫、花、草、ゆうぐ、花びん、まど、先生、友だち?わたしは、「たからものがいっぱいあるな。べんきょうするところじゃなくて、やっぱりたからものがみつかるところかも…」と思いました。そこで、わたしは考えました。「友だち」ってなんだろう?なかよしな人、よく一しょにお人形であそぶ人?本には「じ分と同じところがある、じ分とちがうところがある」のが友だちと書いてありました。わたしと友だちが同じところってなんだろう。こわがり、ポジティブ。ちがうところってなんだろう。しっかりしている、おこらない。考えてみると、友だちと同じところがあったり、ちがうところがあったりする。友だちがふえたらふえるほど、じ分らしくなっていく。そこでわたしはもう一ど考えました。じ分らしさってなんだろう?こわがりな人、プリンぎらいな人、クリームがにが手な人、どんぐりがすきな人、家にいるのがすきな人。
なんだろうって考えると、頭がいたくなる。でも、じ分のい見とちがうことがわかるようになる。考えることはおもしろい。これからもいっぱいなんだろうと考えようと思います。
| 作品名 | 『なんだろうなんだろう』 |
|---|---|
| 作者 | ヨシタケ シンスケ/著 |
| 出版社 | 光村図書出版 |
マザー・テレサと心の飢え
洛南高等学校附属小学校 四年 山本 真央 さん
マザー・テレサは、私の好きな偉人の一人です。でも、この本を読むまでは、貧しい人を助ける優しい人、ノーベル平和賞を受賞した人、ぐらいの認識しかありませんでした。
マザー・テレサは、インドの貧しい人のために働こうと考え、十八歳の時、修道女になるため、聖マリア高等学校の先生になりました。彼女は、先生として働く一方で、スラムの貧しい人たちの生活を目の当たりにしました。そして、心を痛めた彼女は、貧しい人たちのために全てをささげようと決意し、一人でスラムへ行きました。病気にかかり、食べるものがなく、やせ細ったまま死んでいく人たちを助けたい、その一心だったと思います。
私が一番心に残ったのは、貧しくて育てられず捨てられた赤ん坊、体が衰弱して動けない老人にも、たとえ、明日死んでしまうとしても来てもらいたい。誰からも愛されないまま、世話をしてもらえず、死なせたくない。人間にとって最も悲しいことは、貧しかったり、病気やお腹を空かせて死ぬことではなく、貧しかったり、病気だったりするために、誰からも相手にされないことだと伝えているところです。
四年生になって、中高生の自殺、子どもや動物の虐待を新聞やニュース番組で知ると、これまで以上に辛く複雑な気持ちになります。
私は、たまに勉強などで大変だと思うことがありますが、幸せです。でも、自殺や虐待されて死んでいった人や動物は、どんな気持ちだっただろう、幸せだったのかなあと考えると、胸が痛みます。生まれた時のただの偶然に過ぎないのに、世の中は不公平だと、生まれ変わることができればいいのに、と願わずにはいられません。
本当の飢えは、インドやアフリカのような貧しい国にあるのではなく、東京や私たちが暮らす都会にもあるのではないかと、この本を読んで思いました。心の飢えとは、自分が誰からも必要とされていない孤独からくるものだと知りました。ほんの少し誰かを愛して、愛されればいいだけなのに。
マザー・テレサは、孤児の家、死を待つ家、スラムの学校などの活動を通じて、孤児や貧しい人たちの中に飛び込んで、救いの手と、愛の手を差し伸べました。その活動は、全てがうまくいった訳ではなく、脅迫や心無い批判もありました。でも、一歩も引き下がらず、強い意志で生涯貧しい人の心の支えになりました。そんな折れない心と優しさで、一体どれだけの人を救ったのでしょう。
この本との出会いは、私に、これからどんなことができるかを、考えさせるものでした。
現代では、苦労せずに情報や物がすぐに手に入ります。こんな便利で豊かな時代だからこそ、心の飢えが目立っているのかもしれません。もし、この先、孤独を感じたり、周りに悩んでいる人がいれば、この本のことを話そうと思います。きっと悩んでいることが、小さなことに思えるから。
| 作品名 | 『マザー・テレサ かぎりない愛の奉仕』 |
|---|---|
| 作者 | 沖 守弘/作 |
| 出版社 | くもん出版 |
ありのままの自分とは何か
向陽小学校 五年 山口 紗季 さん
「ありのままの自分とは何か」「大人になるとはどういうことか」この作品に出会い、私は心の深いところで何度も考えました。
この物語は、主人公のメス馬ポンコが牧場からにげ出し、エカシの森で生きていく様子をえがいたものです。森の中でポンコは、不思議な生き物や四百年も生きるエカシの大木、カメムシなどと対話をしながらくらしています。自由なくらしを求め、牧場からにげ出したポンコでしたが、冬になり、エサや水がなくなり、牧場のおじさん達の親切のおかげで、エサや水をえることができていたことに気づきます。その人達がいたからポンコは今まで生きることができたのです。本人の気づかない誰かの親切によって、ポンコは生かされていて、それは私達人間も同じです。この誰かの親切なしには、私達は生きていけません。他の人が自分にどれだけの時間を使ってくれているか、気持ちをかけてくれているかがわかって、感しゃができて、自分一人だけの世界ではなくなること、それが大人になるということだと思います。母が以前「大人は自由。でも自由をえるためには責任がともなう。」と言っていました。自由をえる代わりに、自分で生きるための努力が必要になるのだと思います。
物語の中のカメムシの言葉に「生き物は弱い電波のようなものを出し、それを捕まえるアンテナを持っている。人間は頭で考えるからダメだが、ポンコが認めなくても、ポンコの体はどこか遠くへひっぱられ始めている、それを認めないのは頭で考えているから」とあります。この「頭で考えているからダメ」とは一体どういう意味なのか、すぐには答えが出ませんでした。初めは頭で考えずに、自分の思うままに行動することは自己中心的で、自分勝手なことだと思いました。しかし、何度も考えているうちに、周りの人を意識しながらも、自分の本能、感覚、好みを大事にして生きてもいいということなのだと感じ始めました。
物語の最後に「ポンコの足はエカシと反対、牧場の方へ向いている」とあります。ポンコはいやだったはずの牧場に戻ったのです。戻りたくない気持ちと、本能的な体の反応はちがっていました。この本能的な体の反応、感覚をありのままというのでしょうか。私はありのままとは、自分で決めることだと思います。ポンコが最後に自分の意思で牧場に向かったように、誰かに認めてもらうのではなく、自分で決めることだと思います。
私は今まで気づかなかった誰かの親切を意識してみようと思います。周りの人への感しゃとありのままの自分を両立させることはとてもむずかしいことだと思います。自由とありのままの自分を手に入れ、私が大人になる日はいつだろうか。そんな未来の課題を、ポンコは私に残してくれました。
| 作品名 | 『エカシの森と子馬のポンコ』 |
|---|---|
| 作者 | 加藤 多一/作 大野 八生/絵 |
| 出版社 | ポプラ社 |
「二面性の美学」
勝山中学校 三年 山口 真央 さん
四ツ葉のクローバー。これは、稀にしか見つけることができないため、見つけた者には幸運が訪れると言われている。だが、みなさんは四ツ葉のクローバーに隠されたもう一つの意味を知っているだろうか。それは、復讐。何事にも光輝くその裏には、闇がある。そんなことを知らない少女は、神々しく光る赤い靴に人生を踊らされることになる。
アンデルセン童話の一つ、赤い靴。貧しく靴すら買ってもらえなかった少女カーレン。彼女は母を亡くし悲しみに暮れていたが、品のある素敵な奥様に引き取ってもらうことになる。そこでの苦しく、だが、幸せだった壮絶な人生を描いた物語だ。
ある日、カーレンを引き取ってくれた奥様が重い病気にかかった。身寄りのない奥様の看病はカーレンがするはずだったが、赤い靴を履いてダンスパーティーに出掛けてしまった。そのため踊り続ける足を切り落とすことになってしまった。彼女の行動は大切な人を見捨てるような行為に思えるが、私は彼女に共感した。
先日、私の祖父がこの世を去った。私は、病床にいた頃の祖父を見るのがとても怖かった。目を背けたいと思う時もあった。彼女も母を亡くしていて、あの何かが抜け落ちたようなさびしさを知っていたのだろう。だからただその何かを、救いを求めていただけなのかも知れない。美しいもの、私たちの言葉で言うならば好きなものは、私たちを癒し、救ってくれることもある。それがあるから頑張ろうと思えたり、つらいことがあっても乗り越えられたりする。でもその一方で、それに囚われてしまうと周りを見失ってしまうこともあるのだ。
その数日後、赤い靴と別れることができ安心していたのも束の間、カーレンの目の前に再びあの赤い靴が現れた。目の前で生き生きと何にも囚われずに踊り狂う赤い靴。それがずっと追い求めていた自分の姿のように思えて、それと対極的な現実の姿を見せつけられたように感じたのだろう。理想ばかり追い求めてふと周りを見渡せば、彼女を見つめ返す目は一つも無かった。あんなに大好きだった赤い靴さえステップを踏みながら遠ざかっていった。目の前にあるのは、足を失った私、大切に育ててくれた奥様を失った私、全てを失った哀れな私。そこでやっとカーレンは自分の罪の大きさに気づいた。でも、赤い靴が気づかせてくれたことはこれだけではなかったと思う。それは、彼女にとって本当に大切なものだ。不幸という言葉なんて知らない美しい姿ではなく、本当に大切なことは人に大切にされること、その人と一緒にいれることだということに。
彼女自身もそうだったように、本当に大切なものは失ってみないと分からないこともある。それは、あたり前にあったもの、支えてくれたもののような身近な所にあるのだ。それを失ってしまうと彼女のように全て失うことになりうるかもれしれない。
筆者は、光と影のような対比表現を多く用いている。美と恐怖、理想と現実など。筆者は赤い靴をモチーフにして、カーレンの何かにすがってしまう弱さ、理想を求めすぎて現実で幸せを掴めなかった哀れさなど、人の影の部分を強調してかいていた。だが、赤い靴は必ずそんな彼女を救おうと、大切なものに気づかせようとしてくれていた。このように物事には必ず二面性があり、真逆のことのように思えることが表裏一体になっているのだ。
その後、カーレンは罪を償うために教会で働き聖書を熱心に読んだ。そんな彼女を神様は、光の世界へと導いてくれた。闇の中に葬られた彼女だったが、一筋の細くもろい光でも信じて歩き続けたことで光の満ち溢れた場所へいくことができたのだろう。
この話は、残酷な場面が多く怖い話という印象が残っているかも知れないが決してそれだけではない。人の弱さ、人のたくましさといった二面性をテーマにした私たちにとっても身近なお話だ。私たちも細くもろい光の筋を歩いて生きている。それは、魅惑的な光に惹かれ、一歩でも踏み間違えれば闇に落ち、大切なものを失えば音をたてて崩れていく。また、頑張れば、頑張るほどその道は険しさを増していく。でも、彼女のようにその先に光輝くものがあると信じて歩き続けるしかない。だから、その光を繋ぎ止めるような小さな優しさに感動し、そこから突き落とされるようなことに憎悪を膨らます。そんな危うさが、赤い靴を輝かせてみせていたのかもしれない。
| 作品名 | 『あかいくつ』 |
|---|---|
| 作者 | アンデルセン/作 かんざわ としこ/文 いわさき ちひろ/え |
| 出版社 | 偕成社 |